記事を書いたら、祈る がんと闘う記者が考えた
いきさつは忘れたが、あなたは何のために記事を書いているの? と問われたことがある。静岡県の沼津支局で働いていた20代後半。相手はひとつ先輩の女性記者だった。
何を今さらと思い、「世の中を変えるためじゃないですか」と答えると、いきなり「それは違う」とはねつけられた。「それはあなたの思い上がりなの。あなたは傲慢(ごうまん)なの」
彼女は遠くのフリースクールまで通い、そこに集う若者たちに寄り添って連載をするような記者だった。かたや私はといえば、身近な政治や行政のありようなど、どちらかといえば硬めのテーマに関心があった。
そのとき、2人とも酔っていた。だが、彼女の言葉は、酒の勢いばかりではないように聞こえ、思わずあなたはどうなんですかと問い返した。
「書いたら、祈るの」。胸の前で両手を組み合わせ、彼女は続けた。「世の中を『変える』じゃないの。『変わってくれたらいいな』と、祈るの」
「どっちも同じじゃないですか」と言っても、「全然違う。あなたはわかってない」と彼女も譲らない。「傲慢」と批判され、どこか痛いところを突かれたような感触が残った。
◇
こんな20年近く前の、とりとめのないやりとりを持ち出したのは、先日、がん患者から見た参院選のことをコラムに書いたからである。
医師によるインフォームド・コンセント(説明と同意)のように、与野党が自らの政策のリスクも明らかにしたうえで必要性を説くようになれば、有権者はもっと判断しやすくなる――といった内容だ。
たくさん感想をいただいた。興味深かったのは、読んだ人たちの受け止め方が様々だったことだ。
ある後輩記者は「アベノミクスのリスクを語ろうとしない安倍政権に対する、本質的な批判ですね」と言った。
当事者たちからも声が寄せられた。
内閣府副大臣としてアベノミクスの成長戦略づくりに関わった自民党衆院議員の平将明さんは「いまの政策の訴え方では、有権者が比べられないと私も思っていた」。一方、民主党で春まで政調会長をしていた細野豪志さん(現・民進党)も「たしかに、今回の選挙では誰も自らの政策のリスクを語らなかった」とフェイスブックで振り返った。その目線は政権だけでなく、身内にも向けられているように感じた。
◇
コラムで書いたのは、病室や自宅でひとり考えてきたことだ。それがどう読まれるか、影響を与えるかどうかはわからない。ただ誰かに届けばいいと、紙面に載るあてもないまま、一気に書き上げた。
思えば、暗闇の池へ念じながら小石を投げるようなこのときの気分が、かつて言われた「祈る」ということだったのだ。記事で社会をひとつの方向に変えよう、正そうと力めばともすると独善に陥り、かえって読者の胸に響かないかもしれない。記事に思いを込め、読者に届いたらあとはゆだねる。そんな心の持ちようを先輩記者は「祈る」と表現したのではないか。
ともあれ、小石を投じた先からはポチャンという水音が返ってきた。平さんはSNSで細野さんの感想を読み、コラムの提案について超党派で勉強会をするために、連絡を取り出したそうだ。私の知らないところで始まった、こうした動きの行方を見守りたい。
言葉はときに、歳月をへて発芽する。そんな言葉を自分も残せれば、と思う。(野上祐)
◇
野上祐(のがみ・ゆう) 1972年生まれ。96年に朝日新聞に入り、仙台支局、沼津支局、名古屋社会部を経て政治部に。福島総局で次長(デスク)として働いていた今年1月、がんの疑いを指摘され、2月手術。現在は抗がん剤治療を受けつつ、7月に記者として仕事を再開した。
(出所:朝日新聞デジタル(AERA.dotに転載)連載「がんと闘う記者」、2016年8月8日掲載)



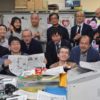
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません